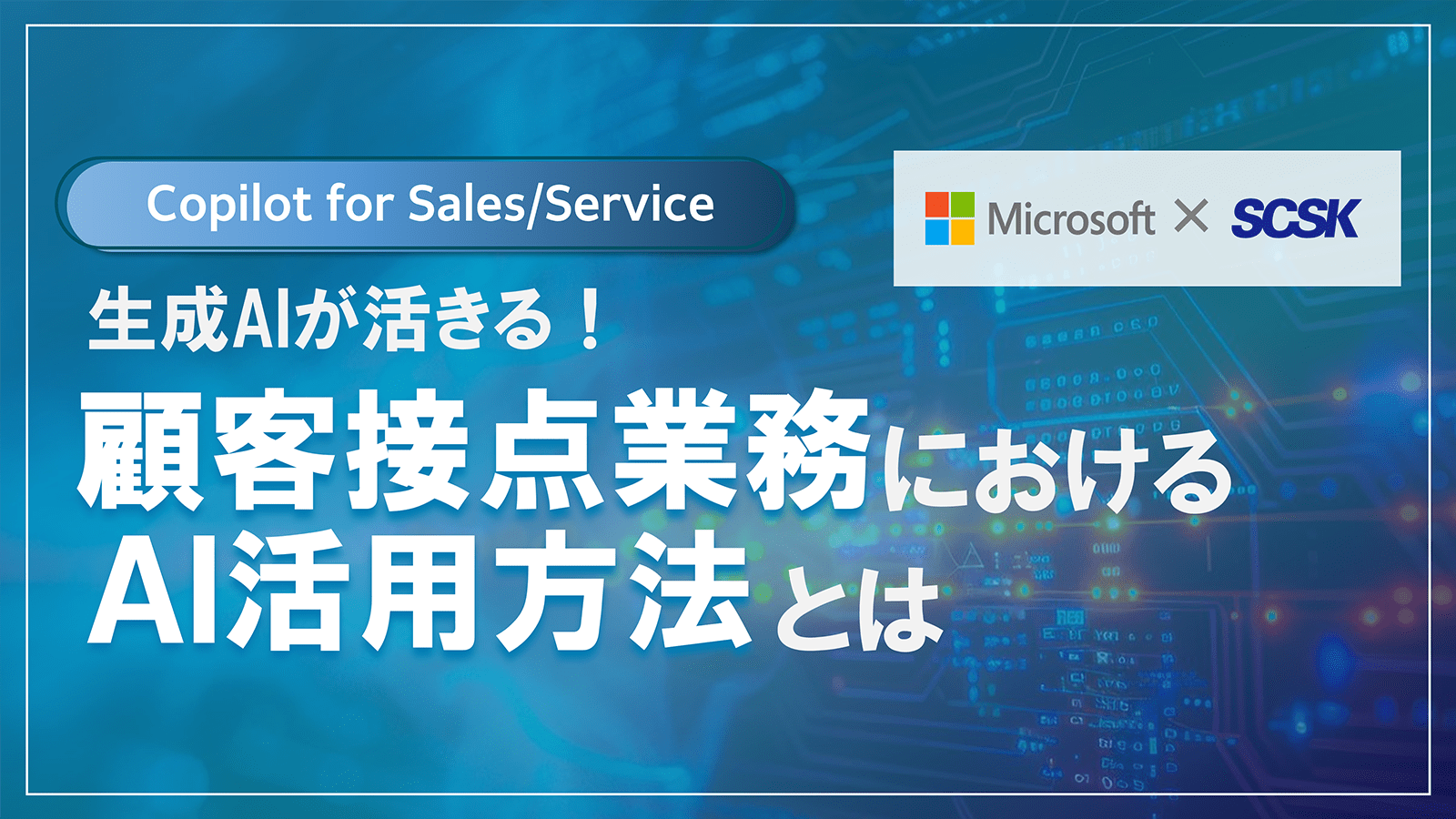SFAとは?
CRM・MAとの違いや導入メリットを簡単に解説!
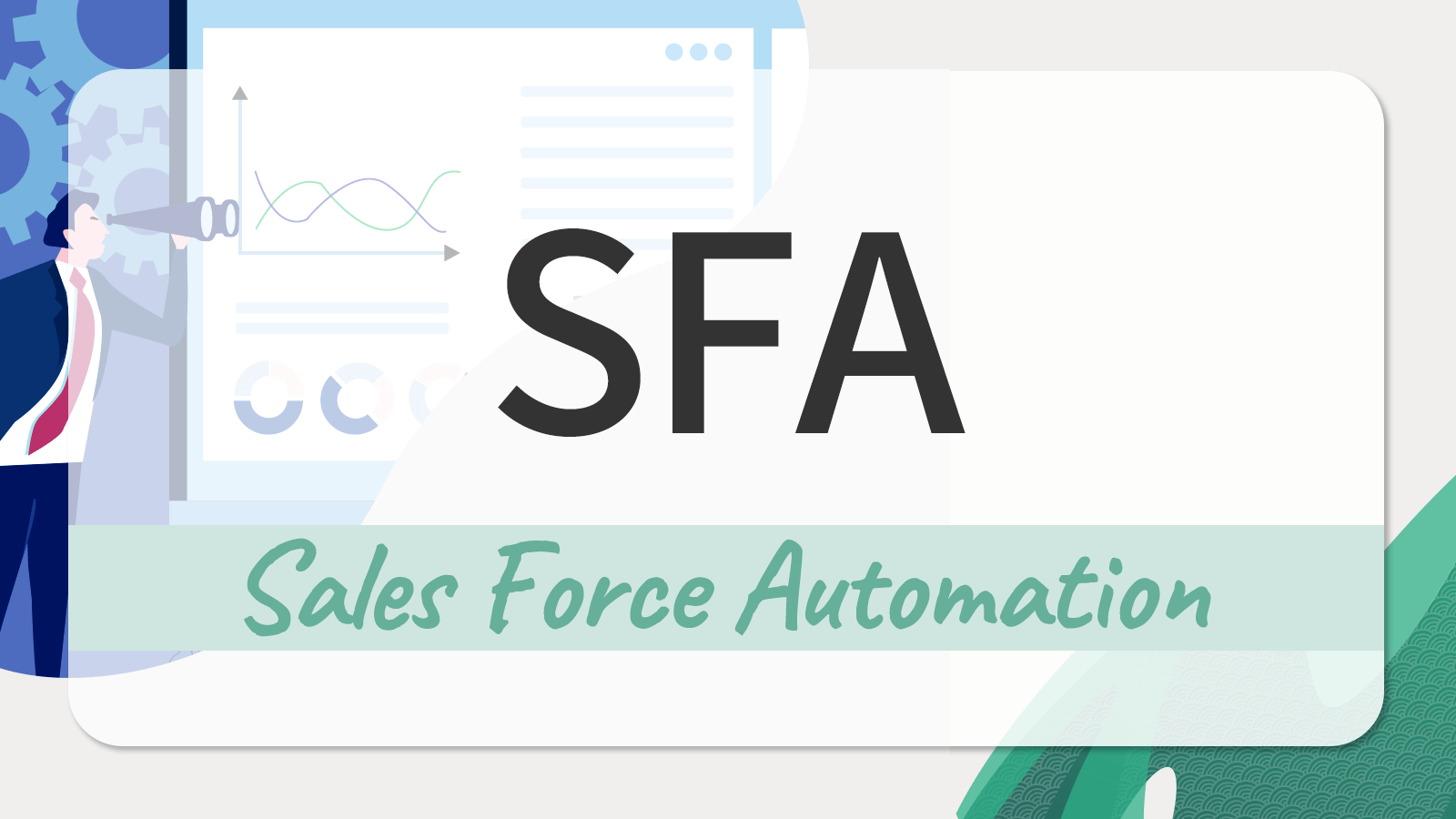
営業部門の生産性や効率性を高めたいと考えたとき、有力な選択肢となるのが「SFA(営業支援システム)」の導入です。SFAは、営業プロセスや商談情報、活動履歴などを一元管理するITツールで、属人化しやすい営業業務を可視化・標準化できる点が大きな魅力です。
この記事では、リーダーやマネージャーとして営業の効率化を目指す方に向けて、SFAの定義やCRM・MAとの違い、主な機能、導入によるメリット・デメリット、ツール選定のポイントなどについて解説します。ぜひお役立てください。
1.SFAとは
SFAとは「Sales Force Automation」の略称で、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。営業活動の進捗や担当者の行動、顧客とのやり取りなどを一元管理し、営業業務の効率化と成果の最大化を目指すITツールです。
SFAを導入すれば、顧客情報や商談履歴がリアルタイムに共有され、チーム全体で営業活動を把握しやすくなります。個々の営業担当者の動きも可視化されるため、マネージャーは適切なタイミングでアドバイスやフォローを行うことが可能です。
さらに、属人化しやすい営業ノウハウを蓄積・共有できる点も、SFAの大きな特徴です。組織全体の営業力を底上げし、安定した売上拡大へとつなげる効果に期待できます。
1-1.SFAとCRMの違い
SFAとCRM(顧客関係管理システム)は、どちらも営業活動に役立つツールですが、目的や機能には明確な違いがあります。
SFAは、営業プロセスを可視化・効率化することに特化した、商談の進捗や担当者の活動内容、売上見込みなどを管理し、営業チームの生産性向上を支援するツールです。見込み顧客(リード)へのアプローチから受注までの流れを対象とし、業務の属人化解消にも貢献します。
一方、CRMは顧客情報や対応履歴を一元管理し、顧客満足度の向上やリピート率の改善を目的としたツールです。受注後のフォローアップや長期的な関係構築に活用され、マーケティングやカスタマーサポートとの連携にも適しています。
SFAは「営業活動の管理」、CRMは「顧客との関係構築」に重点を置いたシステムであり、両者を組み合わせることでより高い成果が期待できます。
1-2.SFAとMAの違い
SFAとMA(マーケティングオートメーション)は、いずれも営業活動の効率化に貢献するツールですが、目的や役割には明確な違いがあります。
SFAは商談の進捗や営業担当者の活動状況、売上予測などを管理するためのツールであり、営業部門が主に利用します。リードが育成された後の商談フェーズを中心に、営業プロセスの可視化と改善を図る役割を担います。
一方、MAはリードを獲得し、購買意欲を高めるまでのプロセスを自動化・効率化するためのツールです。メール配信やWeb行動の分析、スコアリング機能などにより、顧客の興味・関心にあわせた適切な情報を適切なタイミングで届け、購買意欲を高めていくことを支援するもので、主にマーケティング部門が活用します。
SFAは「商談管理と営業支援」、MAは「リードの獲得と育成」に特化しており、両者を連携させることで、営業活動全体の最適化が可能です。
2.SFAの主要な機能
SFAには、営業活動を効率化・標準化するための多彩な機能が備わっています。顧客情報や案件の管理だけでなく、商談の記録、売上予測、スケジュール管理、さらには書類作成までを一元化できる点が特徴です。
ここでは、SFAに搭載されている主な機能について解説します。
2-1.顧客情報管理
顧客情報管理は、SFAの基本となる機能です。会社名や担当者名、連絡先、所在地などの基本情報に加え、問い合わせ履歴やクレーム情報、取引実績といった詳細データも一元管理できます。
営業担当が異動した場合でも、SFA上の情報を確認すれば、誰でも速やかに対応できる体制を構築できます。属人化を防ぎ、営業部門全体で顧客対応の品質を維持できる点が、この機能の強みです。
2-2.案件情報管理
案件情報管理は、見込み顧客とのやり取りの中で発生する営業案件を記録・管理するための機能です。提案内容、営業フェーズ、受注予定日、見積金額などを入力・更新することで、案件の進捗を可視化できます。
各案件について簡単に俯瞰してチェックできるので、成約確度の高い案件を優先して対応する、フォローが必要な案件に人員を振り分けるなどの対応が可能になります。また、営業会議の資料作成にも活用しやすい機能です。
2-3.商談内容管理
商談内容管理は、顧客とのやり取りの履歴や提案内容、課題、見積書の有無などを記録・管理する機能です。営業担当者の活動が詳細に記録されるため、別の担当者への引き継ぎが発生した際もスムーズに対応できます。
また、成約に至った商談と失注した商談を比較分析して今後の営業手法を改善するヒントを探り、営業ノウハウを組織内に蓄積するための仕組みとしても使用できます。
2-4.営業活動管理
営業活動管理は、日々の訪問件数、提案数、アポイント取得数などを記録し、担当者の営業活動を可視化する機能です。数値データを基に、各担当者の行動パターンを分析し、課題点を抽出できます。
たとえば、アポイント率の低さが課題であればトークスクリプトの見直しが必要であると分かります。この機能を使いこなすことで、営業力の強化と業務の最適化を図れるでしょう。
2-5.データ集計・分析による売上予測
SFAは、各案件の進捗状況や受注確度、見積金額などの情報を基に、将来的な売上を予測する機能を備えています。予測値は個人単位から部署・全社単位までさまざまな粒度で算出でき、営業活動の重点配分やリソースの調整に役立ちます。
実績との乖離の分析によって営業戦略の修正が可能になるので、精神論に頼らない、データに基づいた判断を下せるようになります。
2-6.タスク・スケジュール管理
SFAには、営業担当者のスケジュールやToDoリストを管理する機能も搭載されています。個人の予定だけでなく、チーム全体のタスク状況も可視化されるため、ミーティングや同行営業の調整も円滑に行えます。また、リマインド機能により、タスクの漏れを防げます。
営業活動を個人プレーからチームプレーへとシフトさせたい場合に、重要な役割を果たします。
2-7.書類作成
SFAでは、見積書や提案書、営業日報などの各種書類を効率的に作成することが可能です。入力された案件情報を活用すれば、テンプレートを用いてスピーディーにミスの少ない書類作成が可能です。承認フローの設定やメール送信機能とも連携できるため、作成から送付・承認までのプロセスがSFA内で完結します。
書類業務の負担を軽減し、営業本来の業務に集中できる環境を作りたいとき、SFAは便利です。
3.ビジネスにSFAを導入するメリット
SFAを導入することで、営業活動の見える化、標準化、効率化といった多方面のメリットが得られます。情報の属人化を防ぎ、チーム全体の生産性や再現性を高める仕組みが整うため、組織としての営業力が底上げされます。
ここでは、SFAの導入によって得られる代表的なメリットを解説します。
3-1.営業活動を可視化できる
SFAを導入する最大の利点の1つが、営業活動の可視化です。営業担当者が「どこで、誰に、何をしたか」をリアルタイムで記録・共有することで、現場の活動内容が即時に把握できます。
営業活動が可視化されれば、マネージャーは営業進捗やトラブル発生の兆候を早期に把握し、迅速に指示やフォローを行えます。また、客先に訪問する頻度やタイミング、活動の重複・漏れといった「ムダ・ムラ・モレ」を見つけやすくなるため、営業効率の改善にもつながります。
データはグラフや一覧表で可視化され、報告書作成や営業会議の資料としても有用です。SFAによって営業活動が可視化されることで、現場の改善スピードが高まり、成果につながるプロセスを的確に導き出せます。
3-2.営業活動を標準化できる
SFAを活用すれば、営業部門内におけるスキルや知識の標準化が進みます。商談の記録や提案履歴、成果の出たアプローチ方法などをシステム上に集約すれば、属人的になりがちな営業手法を組織全体に展開することが可能です。
たとえば、成約に至った商談と失注した商談の差異を分析することで、成果につながる営業スタイルの共通点を抽出できます。また、優秀な営業担当者の行動プロセスをほかのメンバーが学べるようになれば、全体の営業レベルの引き上げにつながるでしょう。
SFAには、日々の営業活動のナレッジを蓄積する機能があるので、新人育成や教育ツールとしても活用できます。結果として教育コストの削減にもつながり、営業力の再現性を高めながら個人のスキル向上を実現します。
営業組織において情報資産を共有しやすい環境を構築するためにも、SFAの標準化機能は有効です。
3-3.営業活動を効率化できる
SFAの導入は、営業活動の効率化に大きく貢献します。これまで営業担当者が手作業で行っていた日報の作成や情報共有、スケジュール調整といった業務も、SFA上で簡単に処理できるようになります。
たとえば、クラウド型のSFAであれば、外出先からスマートフォンやタブレットを使って情報の登録・確認が可能です。会社へ戻る必要がなくなるので、本人の移動時間を有効活用できるほか、営業マネージャーはリアルタイムで報告を受け取り、即時にアドバイスや承認を行えます。
さらに、過去の商談履歴や提案資料を素早く検索できるため、無駄な作業を削減し、本来注力すべき提案や交渉に時間を割けるようになります。こうしたプロセスの効率化は、営業成績の向上だけでなく、働き方改革の一環としても注目されています。
4.ビジネスにSFAを導入するデメリット
SFAは営業活動を支援する強力なツールですが、導入には注意すべきデメリットも存在します。ここでは、SFA導入時に考慮すべき代表的な2つの課題を解説します。
4-1.コストがかかる
SFAを導入する上で最初に検討すべき課題はコスト面です。多くのSFAツールでは月額課金が基本で、機能によっては初期導入費やオプション機能に追加費用がかかるケースもあります。従来、Excelや無料ツールで情報を管理していた企業にとっては、これらの費用は新たな負担となる可能性があります。
また、システムを安定運用するには、社内環境の整備や操作トレーニング、既存データの移行作業といった準備にも時間と労力を要します。
費用対効果を最大限に引き出すためには、導入前に自社の課題と必要な機能を明確化した上で、トライアル期間を設け、現場との適合性を十分に検証することが重要です。不必要な機能にコストをかけず、運用負担の軽いツールを選ぶことで、リスクを最小限に抑えられます。
4-2.情報を入力する作業が発生する
SFAは営業活動をデータで管理する仕組みであるため、担当者による情報の入力が不可欠です。しかし、この入力作業が営業現場にとって負担となるケースは少なくありません。特に導入初期は操作に慣れておらず、1件の入力に数分~10分程度かかることもあり、1日の営業件数が多ければ、その分だけ負担が大きくなってしまいます。
入力項目が多すぎたり、インターフェースが複雑で操作しにくかったりすると、「面倒なツール」として敬遠され、結果として利用頻度が下がってしまいます。また、SFAの活用目的が社内で共有されていない場合、入力の意義が理解されず、定着しにくくなることもあります。
この課題を解決するためには、初期段階は必要最低限の項目に絞った運用を行い、操作への慣れを優先することが効果的です。加えて、スマートフォン対応や音声入力機能、選択式入力などの機能を活用し、入力の負担を軽減させましょう。導入前に入力作業の必要性を丁寧に説明し、現場に目的意識を持たせることも必要です。
5.SFAを選定するときのポイント
SFAは製品ごとに機能や操作性、サポート体制が異なるため、導入にあたっては慎重な選定が求められます。営業現場に定着し、成果につながるツールとするには、自社の業務フローや課題に合ったSFAを選ぶことが重要です。
ここでは、SFA選定時に確認すべき代表的なポイントを解説します。
5-1.現場の人間が使いやすい
SFAの選定で最も重要なポイントの1つが「現場の営業担当者が使いやすいかどうか」です。いくら多機能でも、実際に操作する営業担当者が「使いにくい」と感じれば、システムは現場に定着せず、データの入力や活用が進まなくなってしまいます。
営業現場では日々の業務に追われており、入力項目が多すぎる、画面構成が複雑、操作が遅いといった使い勝手の悪さは敬遠の原因になります。したがって、直感的に操作できるインターフェースや、スマートフォン・タブレットへの対応といった要素も選ぶときのポイントです。
可能であれば、導入前にPoC期間を設けて、実際に現場の担当者に試用してもらい、使用感や業務への適合性を確認しましょう。現場の率直な意見を拾い上げたツール選びは、SFA活用の成否を左右します。
5-2.ベンダーのサポートが手厚い
SFAは導入して終わりではなく、運用を定着させ成果に結び付けるまでが重要です。そのため、導入後のサポート体制はSFA選定時の大切な判断材料です。導入支援、初期設定、活用アドバイス、トラブル対応など、ベンダーによる支援が不十分だと、システムが社内に浸透せず失敗に終わる可能性もあります。
特に、SFAの操作に不慣れなメンバーが多い組織では、マニュアルだけでは対応しきれない場面も多く発生します。専任のカスタマーサクセス担当や24時間対応のヘルプデスクがあるかなど、サポート内容の質と範囲を事前に確認しましょう。
また、活用ノウハウの提供や運用後の機能追加に対する柔軟性も、サポート体制の一環です。導入実績の多いベンダーや、ユーザーコミュニティが活発な製品を選ぶことも検討するとよいでしょう。
5-3.導入後のカスタマイズ性が高い
SFAは企業ごとの業務フローや営業スタイルに合わせて柔軟にカスタマイズできるものを選びましょう。画一的な仕様のままでは、実際の現場で活用しづらいことも多いので、自社に合った画面構成や入力項目、レポート形式を調整できるかが、運用のしやすさに直結します。
たとえば、既存の営業プロセスに即したステータス分類の設定や、社内の承認フローに合わせた通知機能の調整など、細かな使い勝手の最適化は大切です。これらを実現するには、製品そのものの拡張性に加えて、ベンダーが提供するカスタマイズ対応の範囲や柔軟性も確認しておく必要があります。
特に、業種や規模によって必要な機能や使い方が異なる企業では、一定のカスタマイズ性がなければ運用効率が下がり、定着に失敗するリスクがあります。試用段階で具体的に「ここを変えたい」と思った部分が調整できるかどうかを、ベンダーに確認しておくと安心です。
5-4.ほかのツールと連携できる
SFA単体でも営業活動の管理には効果を発揮しますが、最大限の成果を引き出すにはほかの業務ツールとの連携性も重要です。たとえば、CRMやMA、社内の受発注システムやチャットツールなどと連携できるSFAであれば、業務の無駄を減らし、情報の一元化を実現できます。
特に、マーケティング部門と営業部門が連携している組織では、MAツールとSFAを接続し、獲得したリード情報をスムーズに営業活動に活かす流れを作るのが理想です。また、基幹業務システムと連携すれば、見積・受注から請求・在庫管理までの一連の業務を効率化することも可能です。
SFA選定時には、自社の現行システムと連携が可能か、APIの提供があるか、データ連携の方法や制限事項はないかを詳細に確認しておきましょう。業務全体の最適化を視野に入れた選定が、成果の最大化に直結します。
5-5.高度なセキュリティ機能を持つ
SFAでは、顧客の連絡先や商談履歴、提案内容などの機密情報を多数取り扱うので、セキュリティ対策の強度が大切なポイントとなります。情報漏えいが発生すれば、自社の信頼失墜や顧客への損害につながる恐れがあるため、システム自体の安全性は軽視できません。
選定時には、ログイン時の多要素認証、ユーザーごとのアクセス権限設定、通信データの暗号化、データ保存場所の安全性(国内サーバーの有無)などを確認しましょう。また、サイバー攻撃や内部不正への備えとして、ログの記録機能や操作履歴の監視機能が備わっているかもポイントです。
加えて、過去にセキュリティ事故を起こしていないか、金融機関や官公庁への導入実績があるかといった情報も評価基準となります。万全のセキュリティ対策が講じられているSFAを選ぶことで、安心して業務を展開できる環境を整えられます。
SFAとCXの関係、CXを向上させるためのポイントについては以下でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
6.まとめ
SFAは、営業活動の「見える化」「標準化」「効率化」を実現するための強力なツールです。顧客や案件の情報を蓄積・活用し、組織全体で営業ノウハウを共有できる環境を構築することで、再現性のある営業プロセスが可能になります。ただし、導入には一定のコストや情報入力の負担が伴うため、自社に合ったSFAを慎重に選定することが重要です。
CRMとSFAを一貫して行えるaltcircleの顧客管理・営業支援プラットフォーム(CRM・SFA)サービスは、お客様のビジネスの成長を支援することが可能です。顧客管理・営業支援プラットフォーム(CRM・SFA)の具体的なサービス内容は以下をご覧ください。